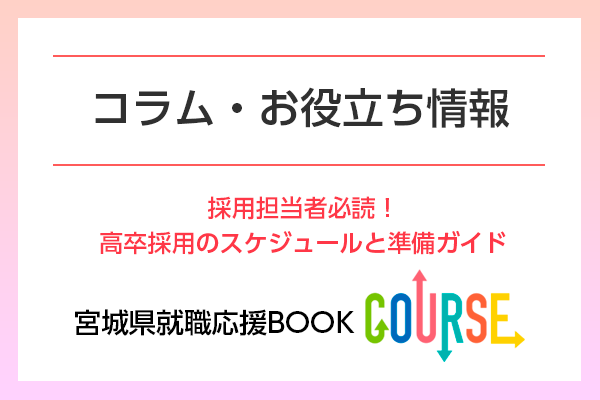はじめに
高卒採用は、大学新卒採用とは異なるスケジュールや方法が求められます。
学校やハローワークとの連携、求人票の作成時期を把握し、計画的に進めることが必要です。
そこで今回は、企業が高卒採用を成功させるために押さえておきたい「高卒の求人を行うためのスケジュールの流れ」について解説したいと思います。
1.高卒採用の全体像とメリット
高卒採用は、高等学校の卒業見込みの学生(主に3年生)を対象とした採用活動になります。
大学新卒採用と比べて募集開始時期や選考開始時期が明確に定められている点が特徴です。
高卒採用のメリットについては、「高卒採用の意義とメリットとは?」で解説していますので、ご覧ください。
2.高卒採用の年間スケジュール概要
高卒採用では、学校側の指導と公的なスケジュールが存在しています。
以下は、一般的な流れの例となります。(ただし、地域や学校により多少前後します)
| 3年生の4月 | ・求人票の作成準備をスタート ・採用計画(募集人数、職種、待遇など)の社内調整など |
|---|---|
| 6〜7月 | ・高校への求人票提出開始 ・学校との連絡・企業説明会の実施、会社見学の受付 |
| 8月 | ・学校側で応募者の選別(校内選考) ・企業見学会や業界説明会が盛んになる時期 |
| 9月 | ・応募受付解禁、面接開始(公的に定められた面接解禁日) |
| 10月〜11月 | ・内定通知を出す企業が増える ・必要に応じて追加募集を行う場合もあり |
| 12月〜3月 | ・入社準備やオリエンテーションの実施 ・卒業後4月入社へ向けてフォロー体制を整備 |
3.高卒採用を進めるためのポイント
3−1.求人票の作成と提出について
・求人票は会社の「顔」
業務内容・勤務時間・福利厚生など、基本的な情報だけでなく、会社の魅力や将来性をしっかり盛り込むことで応募者や学校担当者に好印象を与えます。
・提出時期に注意
「高卒採用」は、例年6月1日よりハローワークの求人受付が開始されます。
作成や申請には時間がかかるため、4月~5月頃から準備を始めるのがおすすめです。
3−2.学校との連携
・進路指導部との関係づくり
高卒採用は、学校の進路指導部が就職指導を行います。そのため、学校訪問や説明会を積極的に行って、企業の特徴や職場環境をしっかり伝えましょう。
・企業見学やインターンの活用
学校側の希望に合わせて見学や短期インターンシップを受け入れると、生徒が企業や業務を理解しやすくなり、応募意欲向上につながります。
3−3.選考・面接の進め方
・面接解禁日は遵守
高卒採用は面接解禁日が定められており、その日以前の面接は原則禁止です。解禁日以降、効率よく面接日程を組みましょう。
・面接方法の工夫
- グループ面接:応募者のコミュニケーション能力などを同時に確認しやすい
- 個人面接:応募者の適性や志望動機を深掘りできる
- 適性検査:会社独自の基準で適性をチェック
4.スケジュール管理のポイント
社内での協力体制を確立しましょう
採用担当者だけでなく、現場のスタッフや管理職との連携が欠かせません。部署をまたぐ協力体制を事前に整えておくと、スムーズに選考を進められます。
早期に必要人数を確定しましょう
「いつまでに何人必要か」を明確にすることで、学校への依頼やスケジュールが立てやすくなります。
内定時期の把握をしましょう
例年9月以降は面接・内定が集中する時期です。書類選考・面接などのスケジュールをあらかじめ組み立て、余裕を持った運営ができるようにしましょう。
5.高卒採用を成功に導くためのコツ
公的スケジュールの範囲内で、できるだけ早期にアプローチ
高校3年生の4月から本格的に就職活動が始まります。早い段階で学校に求人を出すことが、母集団形成の鍵となります。
企業の魅力を“見える化”
職場の雰囲気や先輩社員の声など、生徒が具体的にイメージできる情報を提示しましょう。SNSや動画を活用すると効果的です。
教育・研修制度の充実
高卒生にとって、「入社後にどのように成長できるか」は大きな関心事項です。社員育成やキャリアアップのビジョンを明確に示すことで、応募意欲を高められます。
学校・保護者へのアピール
高卒採用では、保護者の意向も大きな影響力を持ちます。安心感を与えられるよう、給与や福利厚生、休日、職場環境について、丁寧に説明しておきましょう。
まとめ
高卒採用は、時期や選考方法が厳密に規定されているため、計画的に進めることが何より大切です。
- 4月〜6月に求人票を作成し、学校と密に連携
- 9月以降の面接解禁日以降、内定までのスケジュールをしっかり管理し
- 入社後の研修やフォローアップ体制を整え、早期離職を防止
企業と高校、そして生徒との円滑なコミュニケーションが成功の鍵です。
しっかりとした情報提供とサポートを行い、魅力ある企業として認知してもらうことで、質の高い人材を確保できるでしょう。